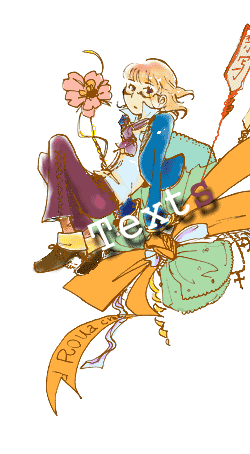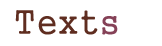焦がれて背中を見つめる、
背中を向けてにらみ合う
いつかは忘れた。
木戸さんを覚えているか、と唐突に伊藤が聞いてきた。
いい加減埒のあかない議論にも疲れ果て、茶でも入れ直そうかと思っていた矢先だった。いよいよ頭の線が外れたかと思いちらりと向かいの伊藤を見やってみると、彼もぐたぁと椅子にへばりついているものの、少なくともこちらをにらみつけてきたから、おそらく一時的な物だろうと願って(なんて癪な単語だ)あぁと手短に答えておいた。
「ふぅん、じゃぁこう、眼を閉じてみて木戸さんの顔がちゃんと浮かぶ?」
伊藤は自身も目を閉じてみせる。
「何が目的だ」
「やだな、目的のない会話はしちゃいけないって言うの。僕とお前の仲じゃない」
「はっきりと細かいところまでとは言わないが、まぁ浮かぶ」
面倒な伊藤の会話はすぱっと打ち切って、答えだけくれてやると伊藤は唇をとがらせた。
「ふぅん、」
「・・・・お前はどうなんだ」
そこで伊藤はぱちっと眼をあける。聞いて欲しいのが丸わかりだ、そうでなければこんな意味のない質問なんぞするものか。あぁなんて面倒な奴。
「もちろん浮かぶさ、頑張って思い出せばね、僕はそれほど馬鹿じゃないもの」
「そうか」
「でもね、最近わかったんだけど、思い出そうとしないと思い出せないんだよね」
そこで伊藤は目の前の冷め切った茶を飲み干す。
「木戸さんって言われて、頭によぎるあの人はいつも」
可笑しいでしょ、どうしてだか上から見下ろしている横顔しか思いつかない。
「お前が木戸さんを見下ろすのか」
「市がお前を見下ろすほど無理があることは知っているよ」
「何故そこで山田が出てくる」
「今は見下ろされているかもね」
ケタケタと不愉快に笑う伊藤はそれでも話をやめる気はないらしい。
「仕方ないのかな、明治に入ってからは木戸さんが座ってて、こう、僕が横に立って紅茶を出したり書類を出したり、お願いです木戸さんその辞表を書くのを今すぐやめてくださいって筆を押さえつけたり、大久保さんが来たりした時にはいつ木戸さんが引き出しから短刀を出すか気が気でなかったし」
なるほど確かに彼は木戸の側によく立っていた。
というよりあの人が座っていることが多かったのだろう。
そうして。
「だから結局」
伊藤はそこで言葉を切って珍しく自嘲気味に笑った。
「あの人は僕のことなんか見ちゃいないんだよ」
「そして僕もあの人のこと、ちゃんと見てたわけじゃないんだ」
そんな今更意味のないことを聞かされた後、お茶がなくなったよ、と文句を言うので仕方なく新しい茶を持ってこさせ、差し出されるがままその湯飲みに注いでやると、湯気がぼんやりと立ち上った。
「ねぇお前は例えば高杉さんの顔を思い出せる」
ここでまた言葉通りに素直に返事をしていては、先刻の繰り返しになること必至だ。
こいつとの無駄な関わりはできるだけ避けたい。だから気にくわなくてもこういうときは求めているとおりの答えをくれてやる。
「思いつくのは背中ばかりだな」
「へぇ」
「あの人が俺たちの方を向くことがあったものか」
あの時代、皆が皆、同じ方向をがむしゃらに目指していて。
「僕もだよ」
伊藤がくっくと笑った。
「ねぇ山県」
それからまたしばらく沈黙があって、湯気がそろそろ消えるかという頃に伊藤が口を開いた。
「もし僕が先に死んで、そのあと何年も何年も経った後に、お前は僕を思い出せると思う?」
「そんなおぞましいこと考えたくもないんだが」
「僕はね、お前が死んでから何年経っても、多分思い出せると思うんだよね」
そこで伊藤はにやりと笑った。
「お前が悔しそうに僕をにらみつけてるような顔とかさ!」
今日一日で一番楽しいと言わんばかりに得意満面でケタケタ一人笑い転げる伊藤にいい加減うんざりしたが、声をかけられたその時からずっと自分が眼を閉じていたことに気づいて、どうしようもなく黙っているしかなかった。
背を向け合っていながら睨み合うことが可能なこの世界の屈折率!
・・・・・・・・・・・・・・・・
突発的にブミガタ。私の技量のなさでこいつらこうやって議論してる図しか思いつかね(笑)
結局伊藤達はどこまでも高杉とか木戸さんとかの後ろをずっと追いかけてる感じ。
私の中では伊藤たちが第二世代で本人もそういうのがあったと思うんだー。
だからタロちゃんたちが第二世代とかって世間で言われてるのを聞いて、
伊藤はそれは僕らのことなのに・・とか思ってるといいよ!
幕末→明治→大正の世代交代的な感じが好きです。
読み物 / 2009.12.04