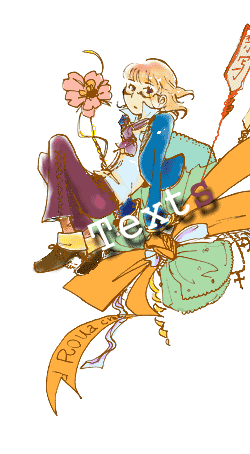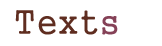「お前のとこの太郎くんさー、相変わらずお前にべったりだよね見ててうっとおしい」
「・・・嫌みか?」
「何が?あぁ、そういえば最近はちょっと反抗期だったねー」
「せめて、独り立ちと」
せめて、どころか独り立ちであって欲しい。いやそうであってしかるべきだ。
後ろに控えるいつの間にか巨大化した、あるのかないのかわからない"閥"を押さえておくためにも
一人前として、扱うべきだとそう思っただけだ。それがある意味後への見せしめに、少しばかり厳しい門出になりそうだとしても。
「ちょっとお父さん-、ダメだよ子供の心はちゃんとわかってあげなきゃ」
どうしたって、お前に構って欲しいだけじゃないの。
「もう、さすがにそんな」
「本当に?大将も年かね、判断力が鈍ったんじゃない」
「そういう自分こそ、見誤ったんじゃないのか」
「何のことさ」
別に、と続けておいた。結局あの後、伊東と彼の押さえる枢密院はどちらかというと山県寄りを維持している。
「私やお前には、一生わからないのだと言っていた」
それは桂が伊東のことについて言った言葉だったが、多分桂自身についてのことでもあっただろう。
ははは、と伊藤はさもバカにしたように笑った。
「相変わらずのおつむだね、"僕ら"にわからないだって?」
「わかってるさ。僕も、お前も、ねぇ山県」
「尊敬してて大好きで愛しくて、追いかけて振り回されて認めて欲しくて、」
そして、と伊藤は天井を仰ぎ見て
「憎まずにはいられないんだろう?」
と言い放った。
山県は手許の湯飲みの中で揺れる水面を見ていた。
天に向かってなんとやら
「ちなみに"僕ら"は逆だね」
「何のことだ」
「イラついて憎らしくて殺したくて、蹴落として振り回して認めるなんてできなくて、」
でもほら、
なんだか愛しいんだろ?
天より先に、目の前の君に向かって、なんとやら!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しつこくてすみません。
読み物 / 2011.08.11